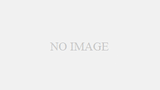生しらすからノロウイルス検出——静岡で何が起きたのか?下水処理の盲点と私たちが知るべきこと
■ 1. 注目のニュースを紹介
2025年3月、静岡県清水区の道の駅で提供された「生しらす丼」を食べた11人が、ノロウイルスに感染していたことが明らかになりました。
感染者はいずれも3月16日と17日にこの生しらす丼を食べており、静岡県の検査によって提供されたしらす自体からノロウイルスが検出されたと報じられています。
静岡県といえば、全国的にも有名なしらすの名産地。駿河湾はしらす漁に最適な環境で、地元民はもちろん観光客にも「生しらす丼」は人気グルメです。そんな名物料理でノロウイルス感染が起きたとなれば、驚きと不安の声が上がるのも当然といえるでしょう。
「新鮮だから安全」「名産地だから安心」――。
私たちが無意識に信じてきた食の安全神話が、今回の一件で揺らぎ始めています。
しかし、今回のケースは決して珍しい特殊事例ではありません。むしろ、日本各地で潜在的に起こりうる問題が表面化したとも言えるのです。
さらに2025年3月には、神奈川県茅ヶ崎市内の飲食店で、生しらすを食べた来店客38人がノロウイルスに感染するという集団感染が発生しました。
提供された生しらすは、地元の漁港で水揚げされたもので、生食用として加工されたものだったと報じられています。現在、保健所が店舗や漁港の衛生状態について調査を進めており、しらすそのものからノロウイルスが検出されたかは未確定ながら、感染者全員が生しらすを食べていたことから因果関係は強いとみられています。
このように、静岡県に続いて神奈川県でも感染事例が確認されたことで、生しらすの生食には一定のリスクがあることが改めて注目されています。
■ 2. ノロウイルスとは?基本をおさらい
ノロウイルスは、冬場を中心に流行する非常に感染力の強いウイルス性胃腸炎の原因ウイルスです。わずか10~100個ほどのウイルス粒子で感染するとされ、激しい嘔吐・下痢・腹痛などを引き起こします。
感染経路としては、
- 感染者の嘔吐物や便からの二次感染
- 汚染された食品(特に生ガキなどの二枚貝)
- 汚染された水や環境
などが代表的ですが、生しらすなどの魚類からも感染することがあるという点は、あまり知られていません。
■ 3. なぜ「しらす」が感染源になるのか?
しらすはカタクチイワシなどの稚魚で、プランクトンを主食とするフィルターフィーダーです。海中の栄養素や微粒子を取り込む過程で、ウイルスに汚染されたプランクトンや有機物を一緒に取り込んでしまうことがあります。
特に問題なのが「生しらす」。
しらすは非常に小さな魚のため、内臓を含めて丸ごと食べるのが一般的。そのため、体内に取り込まれていたウイルスも、加熱処理をしない限りそのまま口に入ってしまうことになるのです。
感染が起こるのは珍しいことではなく、過去にも他県で同様の事例が報告されています。
■ 4. 静岡県の下水処理は問題があるのか?
今回のような事例が起きると、「名産地でなぜ?」という疑問とともに、「下水処理に問題があったのでは?」と考える人も多いでしょう。
しかし、静岡県の下水処理の整備率は全国的に見ても高く、都市部では高度処理も行われているレベルの高い自治体です。それでもノロウイルスの海水汚染が発生してしまう理由は、以下のような複合的要因が考えられます。
つまり、下水処理の質だけでなく、気象・環境・地形的要因などが複雑に絡んでいるのです。
■ 5. 私たちができる対策と意識
食品安全は生産者や行政だけで守られるものではありません。私たち消費者も、「リスクをゼロにする」ことはできなくても、「リスクを避ける知識」を持つことで、自分や家族の健康を守ることができます。
- 信頼できる産地や販売元を選ぶ
- 体調が悪いとき、高齢者・子どもがいるときは加熱調理に切り替える
- 食事前の手洗い、調理器具の衛生管理を徹底する
- 「旬の時期でもリスクがある」ことを前提に食材を選ぶ
「名産地の食材=絶対安全」とは限らない。
そんな現実を知っているだけでも、予防の精度はぐっと高まります。
厚労省・消費者庁の情報もチェック!
ノロウイルスに関する正確な情報は、厚生労働省や消費者庁の公式資料でも確認できます。特に子どもや高齢者がいる家庭では、一度目を通しておくと安心です。
■ 6. まとめ:リスクと共に暮らす時代に必要な知識とは
今回の静岡の事例は、どんなに信頼されている産地でも「食材は自然から来ている」ことを忘れてはならないという教訓を私たちに与えました。
下水処理が高度であっても、自然環境にはさまざまな変動があります。100%の安全を保証することは難しいからこそ、私たち一人ひとりが「食のリスクを正しく理解し、自分で判断する力」を持つことが重要です。
「知らなかった」では済まされない時代。
その一歩として、今回の出来事を通して「安全な食」とは何かを見つめ直す機会にしてみてはいかがでしょうか。